とある病院薬剤師が低亜鉛血症についてわかりやすくまとめてみた
クリックできる目次
Zn(亜鉛)について

Zn(亜鉛)とは
亜鉛とは、人が健康を維持するために必要な栄養素です。亜鉛は全身の細胞内に存在し、
免疫システムが侵入してきた細菌やウイルスを防御するのに役立ちます。
タンパク質およびDNA、つまりすべての細胞の中にある遺伝物質を合成するためにも、亜鉛は体に必要です。
妊娠中、乳児期および小児期の体は、十分に成長・発達するために亜鉛を必要とします。亜鉛は創傷治癒にも有用で、適正な味覚や臭覚にも重要です。
厚生労働省HP より引用
https://www.ejim.ncgg.go.jp/public/overseas/c03/12.html
日本人の亜鉛の食事摂取基準(2025年版)
日本人の食事摂取基準(2025年版)では1日の摂取の推奨量は18~29歳の男性で9.0mg、30~64歳の男性で9.5mg、
65歳以上の男性で9.0mg、18~29歳の女性で7.5mg、30~64歳の女性で8.0mg、65~74歳の女性で7.5mg、
75歳以上の女性で7.0mgとなっています。
また、通常の食事による、亜鉛の過剰摂取の可能性は低いですが、亜鉛の過剰摂取は銅欠乏、貧血、胃の不調など
様々な健康被害が生じることが知られているため、耐容上限量は18~29歳の男性で40mg、30~74歳の男性で45mg、
75歳以上の男性で40mg、18歳以上の女性で35mgと設定されています
健康長寿ネットHP より引用
https://www.tyojyu.or.jp/net/kenkou-tyoju/eiyouso/mineral-zn-cu.html
創傷治癒
創傷とは、身体の表面にできた傷や損傷のことです。
擦過傷(擦り傷)や切創(切り傷)、裂傷などに分類され、さまざまな要因で引き起こされます。
厳密には「創」とは開放性損傷を意味し、「傷」とは非開放性損傷を意味します。
しかし、広義にはすべての損傷を意味することが多いです。
それぞれの傷の状態に合わせて処置が異なるため、看護師には幅広い創傷治癒過程を覚え、それに応じた適切な処置をすることが求められます。
情報かるけるHP より引用
https://karu-keru.com/info/job/ns/wound-healing-process-nursing
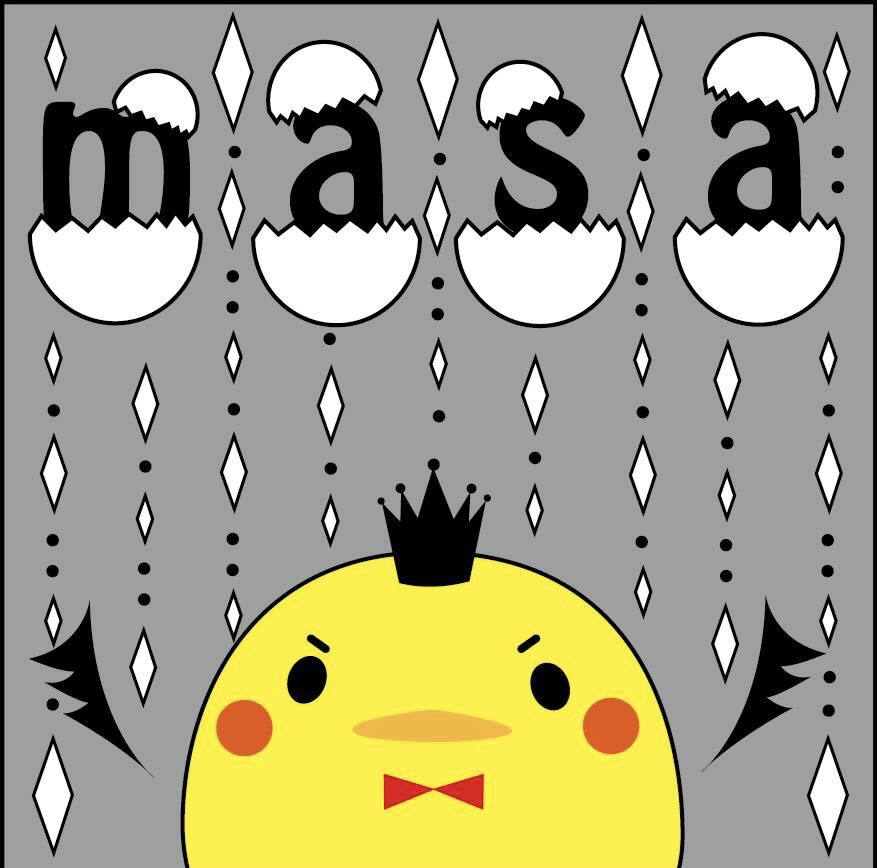
亜鉛は多くのことに関与するんだよね!!
低亜鉛血症について

低亜鉛血症とは
亜鉛欠乏症とは、体内の亜鉛が不足することで皮膚炎や口内炎、脱毛、発育障害、味覚障害・嗅覚障害などさまざまな症状を引き起こす病気です。
亜鉛のはたらきは、皮膚や粘膜の状態を正常に保つ、骨格の発育、味覚や嗅覚、生殖機能、免疫機能の維持など多岐にわたるため、
亜鉛が不足するとさまざまな症状を引き起こします。
体内の亜鉛量を示す指標としては、血液中に含まれる亜鉛濃度(血清亜鉛値)が用いられますが、
亜鉛欠乏症は血清亜鉛値の低下とそれに伴う症状が見られるものを指します。
一方、血清亜鉛値は低いものの、臨床的な症状がないものは“低亜鉛血症”と呼ばれることもあります。
亜鉛は体の中で作り出すことができず、飲食物から摂取しなければならないため、食事療法と薬物療法を行って症状の改善を図ります。
Medical note HP より引用
https://medicalnote.jp/diseases/亜鉛欠乏症?utm_campaign=亜鉛欠乏症&utm_medium=ydd&utm_source=yahoo
原因
亜鉛が不足する原因には、亜鉛欠乏症と低亜鉛血症のいずれも共通して次のようなものが挙げられます。
亜鉛の摂取不足
通常、バランスの取れた食生活を送っている限り亜鉛の摂取量が不足することはありませんが、
神経性食思不振症などによる極端な摂食量の低下や、菜食主義などによって亜鉛不足に陥ることがあります。
また、その他にも経口摂取が困難で経管栄養や静脈栄養を行っている高齢者や、母乳のみで育つ乳幼児も亜鉛が不足しやすいとされています。
亜鉛の吸収障害
亜鉛の吸収障害は、クローン病や潰瘍性大腸炎など腸に慢性的な炎症を引き起こす病気や、肝機能障害を引き起こす病気などが原因で起こります。
また、過剰な食物繊維の摂取も腸管内で亜鉛の吸収を抑制することがあります。
亜鉛の必要量増加
乳幼児期など体重増加が著しい時期や妊娠中は亜鉛の消費量が多くなり、必要量が増します。
特に低出生体重児や母乳のみで育つ乳幼児は、亜鉛不足に陥りやすいといわれています。
亜鉛の排泄量増加
関節リウマチやパーキンソン病、うつ病、てんかん、甲状腺機能亢進症などに使用される薬剤の中には、
亜鉛と結合して尿中への排泄を促す作用を持つものがあります。このため、これらの薬剤を長期間服用していると亜鉛欠乏に陥ることがあります。
また、糖尿病やネフローゼ症候群、腎不全など、腎機能に障害を及ぼす病気も亜鉛の排泄を促すとされています。
Medical note HP より引用
https://medicalnote.jp/diseases/亜鉛欠乏症?utm_campaign=亜鉛欠乏症&utm_medium=ydd&utm_source=yahoo
低亜鉛血症の治療について
亜鉛欠乏症や低亜鉛血症に対する根本的な治療は、主に食事療法と薬物療法です。
低亜鉛血症は症状がなくとも、今後何らかの症状を引き起こす可能性があるため、亜鉛欠乏症と同様の治療を行うことが望ましいと考えられます。
食事療法としては、カキや煮干し、レバー、肉類など亜鉛を多く含む食品を積極的に摂取するよう食事指導が行われます。
一方で、食事療法による亜鉛の補充のみでは亜鉛の不足が改善しない場合は、薬物療法として亜鉛製剤による亜鉛の補充が行われます。
投与量は臨床的な症状とその重症度によって異なるため、専門医への相談が必要です。
Medical note HP より引用
https://medicalnote.jp/diseases/亜鉛欠乏症?utm_campaign=亜鉛欠乏症&utm_medium=ydd&utm_source=yahoo
亜鉛補給製剤の詳しい記事はこちら
亜鉛補給製剤一覧
当院で利用している主な亜鉛補給製剤を掲載していきます。
<内服薬>
プロマックD錠75(ポラプレジンク)[1錠当たり17mg亜鉛含有]
ノベルジン錠25・50[1錠当たり25・50mg亜鉛含有]
ジンタス錠25・50[1錠当たり25・50mg亜鉛含有]
臨床現場で病院薬剤師として思うこと

亜鉛について意識するようになったのは褥瘡関連の業務を行うようになってからです。
病院薬剤師として褥瘡対策委員の業務を行っている際に入院患者に褥瘡に困っていた高齢者が多かったです。
褥瘡を持ち込んだ、当院で発生した患者それぞれ原因がありますが
その原因の1つとして亜鉛欠乏症の状態であることが多かったため
当院では褥瘡患者に対して迅速に亜鉛の血液検査を行い、亜鉛の補給を行っています。
そのような仕組み作りも病院薬剤師の業務の1つだと感じています。
さいごに
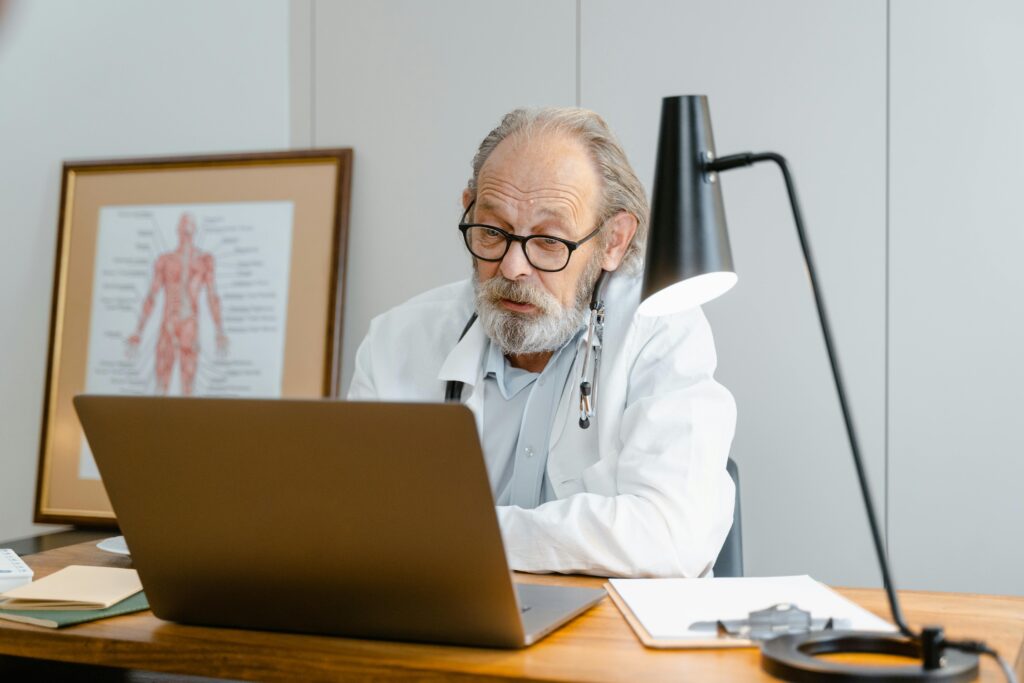
生きているうちに病気になることはあると思います。
その際にどのような対処をすれば良いのか不安に思いながら周りに相談をしたり
自身でインターネットで検索して調べる方は多いと思います。
その1つのお助けツールとしてこちらの記事を参考にして頂けたら嬉しいです。
