とある病院薬剤師がてんかんの病態、治療薬についてわかりやすくまとめてみた
クリックできる目次
てんかんとは

てんかんとは、脳が一時的に過剰に興奮することで、意識消失やけいれんなどの“てんかん発作”を繰り返し引き起こす病気のことです。
私たちの脳は数百億もの神経細胞によって成り立っており、神経細胞が電気的な興奮を引き起こすことでさまざまな情報が伝達されていきます。
てんかんは、神経細胞の電気的な興奮が過剰に発生する部位が生じ、脳のはたらきに異常が引き起こされることによって発症します。
てんかんには症状の現れ方や原因によってさまざまなタイプがあり、乳幼児から高齢者まで全ての年代で発症する可能性があります。
タイプは、画像検査などではっきり原因が分からないタイプと画像上で異常を示すタイプに大別されます。
後者は外傷による脳へのダメージ、脳卒中、脳腫瘍、アルツハイマー病など脳の病気によって引き起こされます。
乳幼児や小児は原因が分からないタイプが多く、高齢者は病気や外傷によるタイプが多いことが特徴です。
てんかんの症状は人によって大きく異なりますが、多くは適切な治療を行うことで発作を抑制し、問題なく社会生活を送ることができるとされています。
一方で、頻繁に発作を繰り返して徐々に脳の機能自体が低下していくケースでは、症状に応じて適切な社会的支援を受ける必要があります。
Medical note HP より引用
https://medicalnote.jp/diseases/てんかん?utm_campaign=てんかん&utm_medium=ydd&utm_source=yahoo
原因
てんかんは、脳の神経細胞が過剰な電気的興奮を引き起こすことによって起こります。過剰な電気的興奮が生じる原因はさまざまです。
近年の遺伝子診断の進歩により、分類や用語が変わってきています。
成人発症てんかんの4割は今なお原因不明ですが、近年の遺伝子診断の進歩により“素因性てんかん(以前の特発性てんかん*)”が
遺伝子との関連が指摘されています。
一方、以前“症候性てんかん“と呼ばれていたてんかんは頭部外傷、脳出血や脳梗塞、脳腫瘍、
皮質形成異常といった脳の構造的な異常や脳炎などの感染、免疫の異常、または代謝の異常が原因であると考えられています。
症状
てんかんを発症すると、意識消失やけいれんなどの“てんかん発作”が繰り返し引き起こされるようになります。
発作症状の現れ方は非常に幅が広く、神経細胞の異常興奮が生じる部位や強さによって大きく異なります。
発作の主な分類としては、脳全体が同時に巻き込まれる全般発作と、脳の一部から発作が生じる焦点性発作(部分発作)があります。
焦点性発作は、発症部位がつかさどる機能に何らかの異常が現れるようになります。
具体的には、手や足の運動をつかさどる部位に発症した場合は手足のけいれんが生じ、
視覚をつかさどる後頭葉に発症した場合は視覚や視野の異常といった症状が現れるようになります。
また、側頭葉などに波及した場合は、けいれんしなくても開眼したまま意識を失い動作が停止する、
手足をもぞもぞ動かしたり口をもぐもぐさせたりするなど、見た目では分かりにくい意識消失発作をきたすことも少なくありません。
焦点性の場合も、神経細胞の異常興奮が脳全体に広がっていくケースもあります。
このような場合には、意識消失や全身のけいれんといった症状が現れます。
発作自体は通常数十秒から数分で自然に収まりますが、発作終了後もしばらく意識が朦朧としていることが少なくありません。
患者自身はこのような発作が生じている最中の記憶はないとされており、車の運転中などに発症することで思わぬ事故を引き起こすケースがあります。
検査・診断
脳波検査
てんかんの診断に必須の検査です。頭皮にいくつかの電極を装着し、脳の神経細胞の電気的な活動を波形として記録します。
てんかん患者では、発作が生じていなくても脳波で異常な電気活動がみられることがあります。
なお、一般的な脳波検査は暗く静かな室内で安静にした状態で行われ、てんかん発作を誘発するために光を点滅させる、
過呼吸を行う(最近は新型コロナがあり避けることが多い)などの負荷をかけながら反応を評価する検査も多くの場合行います。
外来の脳波は30分~1時間程度であり、脳波中にてんかん発作を同定することは通常難しいです。
てんかんを診断するために発作を脳波で確実に同定しなければならない場合はてんかんセンターに入院し、
数日から1週間脳波とビデオを同時記録する“ビデオ脳波”検査がなされる場合があります。
画像検査
脳自体に腫瘍などてんかん発作を引き起こす病気などがないか調べるために、CTやMRIを用いた画像検査が行われます。
一部の症例では、さらに詳しくてんかんの焦点を調べるのに、脳血流検査(SPECTなど)や脳の代謝をみるためのPET、
深部のてんかん性異常を検出するための脳磁図(MEG)を行うこともあります。
血液検査
てんかんと似たような症状は、一部の薬剤による影響・中毒や、低血糖や電解質の異常などによって引き起こされることもあるため、
それらの病気を除外する目的で血液検査も行うことが一般的です。
Medical note より引用
https://medicalnote.jp/diseases/てんかん?utm_campaign=てんかん&utm_medium=ydd&utm_source=yahoo
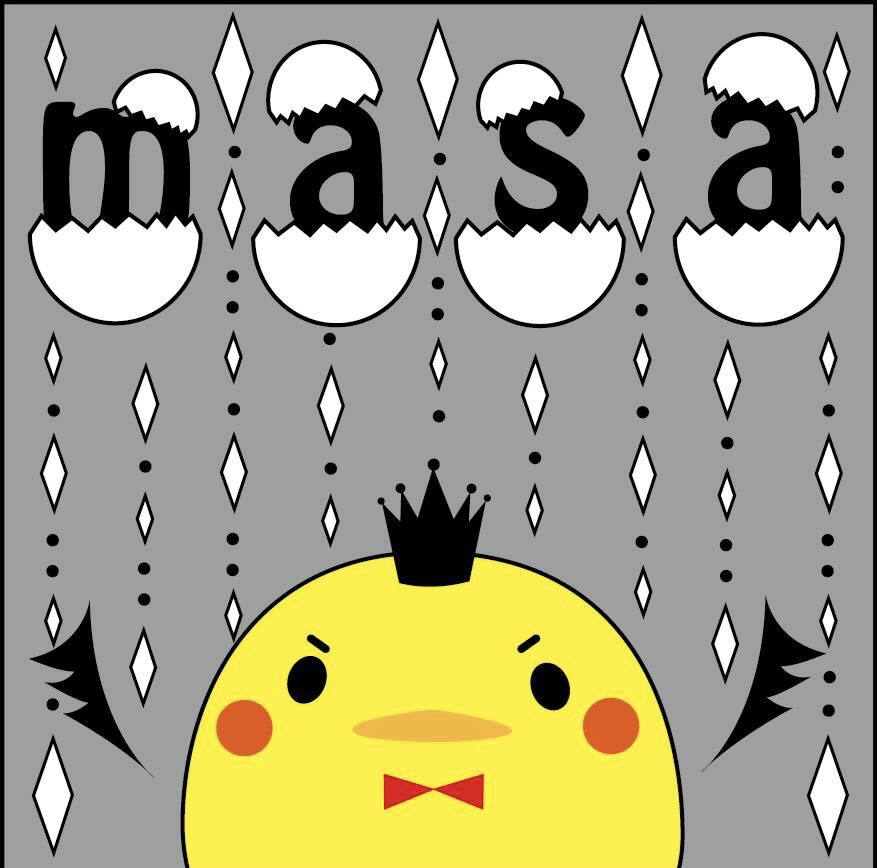
てんかんの治療薬を服用されている高齢者の患者よく見かけます!
てんかんの治療について

てんかんの治療は基本的に神経細胞の異常興奮を抑える作用を持つ抗てんかん薬の内服治療が行われます。
多くは、抗てんかん薬の服用を続けることでてんかん発作を抑制することができ、通常の社会生活を送ることができるようになります。
一方で、複数の抗てんかん薬の服用を続けても発作が難治に経過する場合があり、それに対してはてんかん外科治療が有効な場合があります。
発作の起始が明確に同定された場合、異常興奮が生じている脳の一部を切除する手術(焦点切除術)が有効です。
内側側頭葉てんかんに対する海馬扁桃体切除術や側頭葉切除術は高い確率で発作のコントロールが得られることが証明されています。
てんかん外科治療には、脳の手術以外に迷走神経刺激装置植え込み術もあります。
てんかん病巣の切除が困難な場合、頸部の迷走神経に電極をまき、ペースメーカーのような発動機を胸部の皮下に留置し常時刺激を行うことで、
発作の頻度を減らしたり発作の程度を軽くしたりする効果があります。
そのほかにも、糖や炭水化物を制限して脂質の多い食事を取る“ケトン食療法”、小児のウェスト症候群に対して
副腎皮質刺激ホルモン(ACTH)を注射する“ACTH療法”もてんかん発作を抑える作用があるとされており、
薬物療法と併用して行われることがあります。
てんかんの治療薬について

初回てんかん発作で薬物療法を開始するべきか?
初回の非誘発性発作では以下の場合を除き原則として抗てんかん薬の治療を開始しない。
◆ 神経学的異常、脳波異常、脳画像病変ないしはてんかんの家族歴がある場合
◆ 患者の社会的状況、希望を考慮する場合
◆ 高齢者の場合
◆ 2回目の発作が出現した場合
新規発症部分てんかんでの選択薬について
新規発症てんかんでの抗てんかん薬の治療は、通常単剤で治療を開始する。
第一選択薬:カルバマゼピン、ラモトリギン、レベチラセタム、ゾニサミド、トピラマートが推奨される。
第二選択薬:フェニトイン、バルプロ酸、クロバザム、クロナゼパム、フェノバルビタール、ガバペンチン、ラコサミド、ベラパミルが推奨される。
各医薬品の詳しい記事はこちら
新規発症全般てんかんでの選択薬について
全般性強直間代発作
前ぶれもなく突然起こることがあります。全身が硬くなり、細かなけいれんが左右対称に10~20秒くらい続きます(強直期)。
手と足は強く突っ張り、身体はのけぞり気味になります。
その後、細かなけいれんから次第にリズミカルな動きになり、30~60秒くらい続きます(間代期)。
強直期には呼吸は止まっていますが、間代期にはいると浅い呼吸から徐々に深い呼吸になるにつれて、
口の中の唾液を同時に吹き出してきます。また尿や便をもらすこともあります。
その後、多くは眠りに移りますが、もうろう状態に移ることもあります。
てんかん情報センター HP より引用
https://shizuokamind.hosp.go.jp/epilepsy-info/news/n2-6/
第一選択薬:バルプロ酸
第二選択薬:ラモトリギン、レベチラセタム、トピラマート、ゾニサミド、クロバザム、フェノバルビタール、フェニトイン、ベラパミル
欠伸発作
それまで行っていた動作を突然止め、ややうつむいて、表情がうつろになります。
そして目を開いたまま上の方をじっと見つめたり、手に持っていた物を落としてしまったりします。
発作が軽い場合には、それまで行っていた動作をゆっくり続けたり、また、簡単な質問には返事をすることもあります。
発作が終わるとすぐに通常の状態に戻ります。
この発作はごく短いので、患者さん自身も周囲の人々も気づかないことがあります。ストレスがある時や緊張している時より、
平静時やくつろいでいる時に起きやすい発作です。
てんかん情報センター HP より引用
https://shizuokamind.hosp.go.jp/epilepsy-info/news/n2-6/
バルプロ酸、エトスクシミド、ラモトリギンが推奨されている。
ミオクロニー発作
両方の上肢や下肢・足が0.5秒以内のごく短い時間、同時に一瞬ピクッと動きます。
このような時、患者さんは「今きた」「今、電気が走った」と表現することがあります。
この発作が非常に強い場合には、足払いをされたように転倒することがあります。
物を持っている時に、上肢に発作が起きた場合には、持っているものが飛んでしまいます。
てんかん情報センター HP より引用
https://shizuokamind.hosp.go.jp/epilepsy-info/news/n2-6/
バルプロ酸、クロナゼパム、レベチラセタム、トピラマートが推奨されている。
各医薬品の詳しい記事はこちら
臨床現場で病院薬剤師として思うこと

精神病院に限らず、総合病院で抗てんかん薬を使用している患者は多く入院されます。
入院中は正しく内服薬を服用しているので急に発作が起こることはあまりありませんが
希に発作により、アレビアチン注が急遽処方されるケースがあるため注意が必要です。
また、アレビアチン注の溶解方法、投与方法については多く病棟から相談があるので
適切に伝えるための知識を備えておくことが大切になります。
さいごに
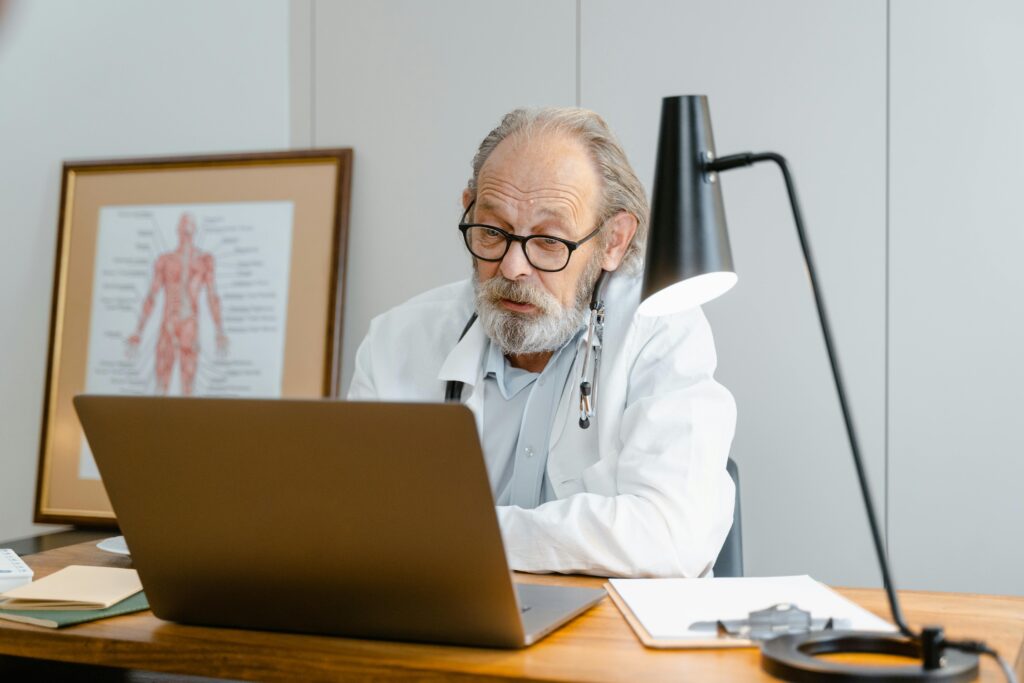
生きているうちに病気になることはあると思います。
その際にどのような対処をすれば良いのか不安に思いながら周りに相談をしたり
自身でインターネットで検索して調べる方は多いと思います。
その1つのお助けツールとしてこちらの記事を参考にして頂けたら嬉しいです。

